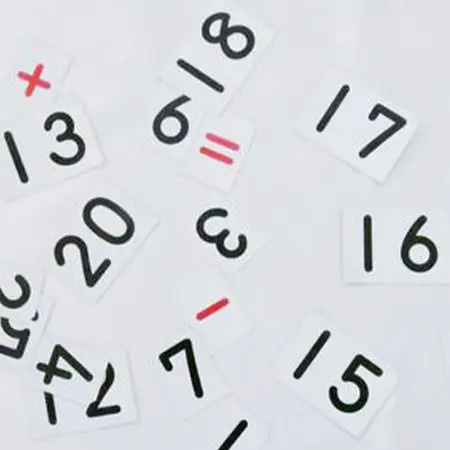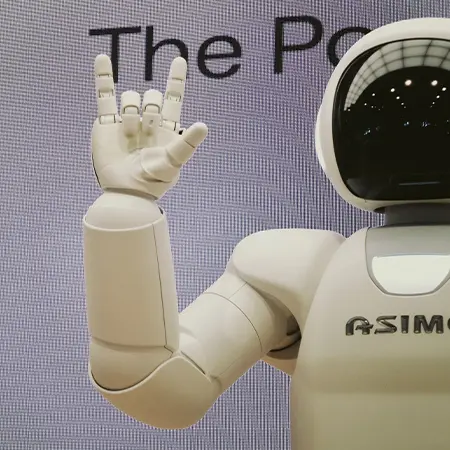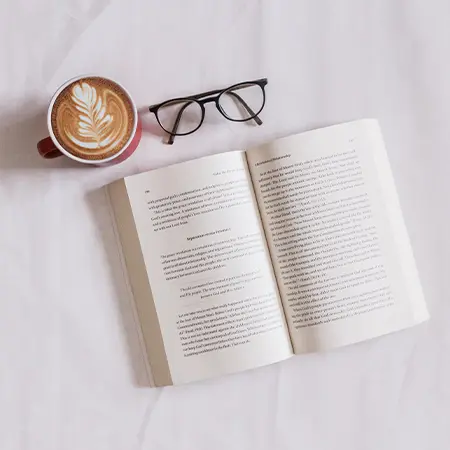傾眠は、昨晩よく寝ていた高齢者が、翌日まだ陽が高いにも関わらず、常にうとうとしてしまう状態です。
体を揺すったり、耳元で声をかけたりすれば、すぐに目覚めますが、しばらく放置していると、いつの間にかまた眠ってしまいます。
特に認知症の高齢者や、薬の副作用などで見られる症状です。
傾眠傾向になりやすい原因を以下にまとめてみました。
多少の傾眠傾向は、年を追うごとに自然に起こります。
頻繁に眠気に襲われたり、健康上に問題が生じたりしなければ、心配することはないと思います。
若年層でもよく見られますが、かぜ薬を飲むと眠くなるように、普段から服用している薬の副作用が働いていることも考えられます。
認知症の症状のひとつに、記憶が抜け落ちたり、理解力や判断力の低下など、脳の働きの低下があります。
これらが引き金になり、起きている時間でも脳の働きが鈍くなり、傾眠傾向に陥ると言われています。
高齢者は身体機能が低下しやすく、脱水状態になりやすいと言われています。
脱水状態になると、意識が朦朧として脳の働きが鈍くなるため、傾眠傾向に陥りやすくなります。
何かしらの病気を患っている場合には、弱っている身体が睡眠を求める可能性もあります。
頭に強い衝撃を受け、頭蓋骨の下にある硬膜と脳の間に血腫ができてしまい、脳を圧迫してしまう症状です。
血腫がごく小さいものであれば、自然に回復することもありますが、頭痛や嘔吐がひどかったり、歩行障害が起きたりするなどの場合には、外科手術が必要になります。
傾眠が必ずしも良くない症状とは限りませんが、傾眠傾向により急な体調の変化や、言動の急な変化が見られるような場合は、すぐに医師に相談しましょう。

不明確な傾眠傾向が続くようであれば、医師に相談するようにしましょう。
慢性硬膜下血腫のように緊急を要する事象でなければ、一時的な原因であることも考えられます。
脱水症状の場合には、経口補水液を補うことで改善することもあります。
普段から水分補給をしておくことは、傾眠傾向の予防や熱中症の予防にもなりますので、朝起きてから十分に水分を摂るようにしておきましょう。
また、傾眠傾向の強い高齢者の食事は、食事中に傾眠されてしまうと、誤嚥になる危険があります。
生活リズムを把握して、傾眠にならないときを食事の時間にするなど、工夫が必要かもしれません。
まずは、傾眠の原因がどこにあるかを探り、必要に応じて医師に相談するようにしましょう。