高齢者に多い誤嚥事故は、介護や医療の現場でも注目されており、転倒や転落に次いで多い事故です。
誤嚥は、食べ物や飲み物が気管に入ることで重大な健康問題を引き起こすことがあります。特に高齢者は嚥下機能が低下しやすいため、日常生活におけるリスクは常に存在し続けます。
ここでは、誤嚥の原因とその予防方法、事故が起きた際の対処法など、知っておくべき重要な情報を説明しています。
※記事の一部はChatGPTで作成しています。

誤嚥は誤った経路で嚥下が起こり、気管や肺に異物が入り込み、咳・窒息、さらに重度の場合は、肺炎を引き起こす原因となることがあります。
嚥下機能が低下しやすい高齢者は、神経系の疾患や筋肉の衰えなど、さまざまな健康問題に起因することがあり、誤嚥をより頻繁に起こす要因となります。
誤嚥は重大な健康問題に直結することがあるため、理解と適切な対策が重要です。
■ 嚥下機能の低下

嚥下機能の低下は、筋力の衰えや筋肉の協調性の損失、または神経制御の障害により発生します。年齢の増加と共に自然と発生することが多く、脳卒中やパーキンソン病、多発性硬化症などの神経学的条件や頭頸部のがんの治療後などにも見られることがあります。
嚥下機能の低下は、食べ物や飲み物が正しい経路(食道)ではなく気管に入りやすくなるため、誤嚥のリスクが高まります。
■ 主な症状や疾患

誤嚥は、特に脳卒中やパーキンソン病、ALS(筋萎縮性側索硬化症)などの神経系の病気に見られます。これらの疾患は嚥下筋の弱化や神経制御の問題を引き起こし、自然な嚥下反射の損傷につながります。さらに認知症を患っている高齢者は、嚥下のタイミングを見極める認知能力が低下しているため、誤嚥を誘発しやすくなります。
■ 日常生活でのリスク
日常生活において誤嚥を引き起こすリスクには、下記のような状況が挙げられます。
- ✓ 急いで食事をする
- ✓ 不適切な姿勢で食事をする
- ✓ 硬い食物や大きい食物が含まれている
- ✓ 話しながら食べる
- ✓ 疲労や注意力の散漫な状態で食事をする
- ✓ 大きな錠剤やカプセル薬の服用時
- ✓ 唾液をうまく飲み込めない
- ✓ うがいや歯磨き時に水が気管に入る
誤嚥が起きたときは状況の重大性に応じて異なります。適切に対処できるよう事前に情報を得ておくことが大切です。以下は一般的な対処方法になります。
| ▼ STEP1 | |
 |
背中をたたく人は誤嚥をした場合、本能的に咳をしますが、詰まり方によっては咳が出にくいこともあります。その際は咳を促すように背中をたたいてあげるようにします。口や鼻から息を吸わせますが、呼吸が困難な場合は直ちに次のステップに進む必要があります。 |
| ▼ STEP2 | |
 |
ハイムリック法背中をたたくだけで異物が取れない場合は、ハイムリック法(腹部突き上げ法)を行います。この方法は気管に詰まった異物を強制的に取り除くためのものですが、正しい方法を知る必要があります。誤った方法で行うと内臓に損傷を与える恐れがあるため、訓練を受けた人による実施が推奨されます。 |
| ▼ STEP3 | |
 |
医療機関への連絡基本的な応急処置後も異物が気道に残っている場合や呼吸困難が続いている場合は、直ちに救急車を呼び、医療機関での迅速な対応が必要です。救急車を呼ぶのをためらう方が少なからずおりますが、対応が遅くなるほど命の危険度が増すため、ためらわず行動しましょう。 |
| ▼ STEP4 | |
 |
経過観察異物が除去された後も、咳や声のかすれ、呼吸の異常など改善が見られない場合は、まだ気管や肺に異物が残っている可能性があります。他にも肺炎やその他の呼吸器合併症のリスクも考えられるため、医療機関で受診することが重要です。 |
誤嚥の多くは食事のときになりますが、食事の際にいくつか工夫をすることで、誤嚥の発生を少なくすることができます。誤嚥を予防するための具体的な方法は以下の通りです。
■ 食事の時間や調理方法を工夫する
食事の時間は急がせずに食べることが大切です。調理方法に関しては、食べやすい柔らかさやサイズに調整し、飲み込みやすい形状にすることが重要です。例えば硬い食品は柔らかく煮る、大きなものは小さく切るなどの工夫が有効です。また、とろみを加えることで液体の誤嚥を防ぐこともできます。
■ 食事の姿勢と食器
正しい食事の姿勢を保つことは誤嚥予防に不可欠です。座って食べる際は、背筋を伸ばし首が少し前傾になるように調整します。食器については、使用する方のニーズに合わせて、持ちやすく安定した食器を選ぶことが良いでしょう。特に底が重く滑りにくい食器や深めの皿を使用するのがおすすめです。
■ 口腔内を清潔に保つ
口腔衛生は誤嚥予防において非常に重要です。定期的な歯磨きや必要に応じて歯科健診による口腔ケアを受けることで、口腔内の感染リスクを減らし、より効果的に飲み込むことができます。舌の清掃も含め食事の前後に口腔ケアを行うことを習慣化します。
■ 誤嚥予防トレーニング
嚥下筋を鍛えるトレーニングや、適切な嚥下テクニックを学ぶことが勧められております。言語聴覚士や専門のリハビリテーションスタッフによる指導を受けることで、効果的な誤嚥予防が可能になります。Youtubeでも多くの関連動画があり、誤嚥予防のサポートとしても学ぶことができます。ただし嚥下時の正しいタイミングや、食事をする際の呼吸法など、実際に自分の動きが合っているか判断できないため、一度は指導を受けておくことをお勧めいたします。
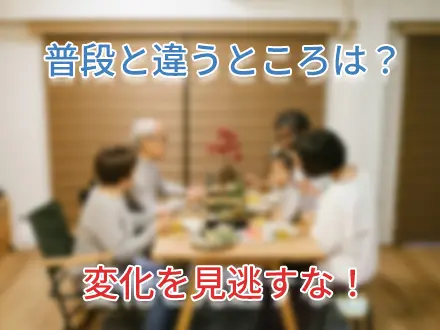
誤嚥の早期発見は重要であり、特定のサインと症状に注意を払うことで、合併症を防ぐことができます。毎日の健康状態を気にしながら細かい仕草や行動で変わったところがないか見極めることが重要です。
以下は、誤嚥が疑われる場合に見られる一般的なサインと症状になります。
食事中や飲水後に連続して咳をする場合は、誤嚥の典型的な兆候です。特に食事中の咳は、食べ物や飲み物が気道に入った可能性があるため注意が必要です。
声がかすれるまたは湿った音がする場合は、液体や食べ物が気管に入り声帯周辺に影響を与えている可能性があります。
咳を伴う呼吸の苦しさや鼻をすするような呼吸音が聞こえる場合は、気道が部分的に塞がれている可能性があります。
酸素の不足が原因で顔色が青白くなることがあります。これは医療的な緊急事態を意味する可能性があるため、すぐに救急車を手配して医師の診察を受ける必要があります。
胸の圧迫感や痛みがある場合は、気道に何かが詰まったことによる可能性があります。呼吸の状態を確認しながら誤嚥が起きたときの対処方法を実践する必要があります。
誤嚥後に発熱が見られる場合は、誤嚥性肺炎の発症を示唆している可能性があります。感染が肺に広がった場合、発熱以外にも全身の倦怠感が伴うことがあります。

誤嚥は嚥下機能が低下しやすい高齢者に多く見られ、重大な健康問題を引き起こす可能性があります。適切な予防策を講じることは、誤嚥による合併症を防ぎ生活の質を維持するために非常に重要です。
頻繁に誤嚥が起こる場合は、食事の調理方法から正しい姿勢、口腔ケアに至るまで日常生活でできることは実践しておくようにしましょう。また誤嚥の早期サインに注意を払い、異常が見られた場合には迅速に医療機関を受診することが重要です。
介護者や家族が誤嚥の知識を持ち、誤嚥のリスクを理解し効果的な対策を講じて、愛する人の安全を守っていきましょう。





















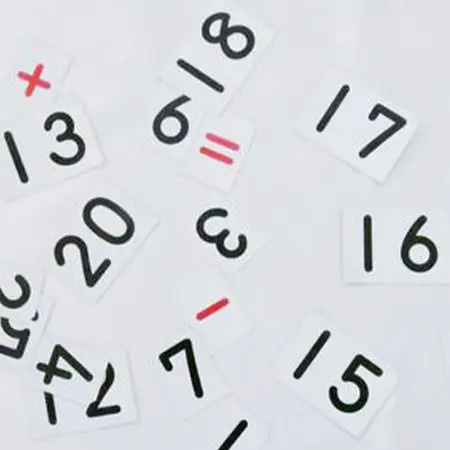

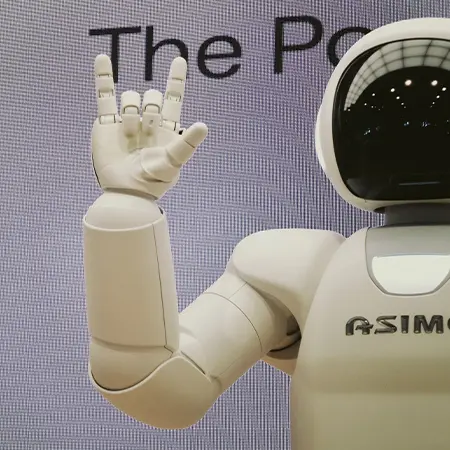





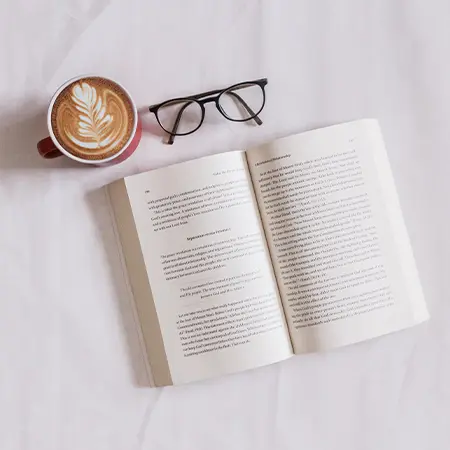

























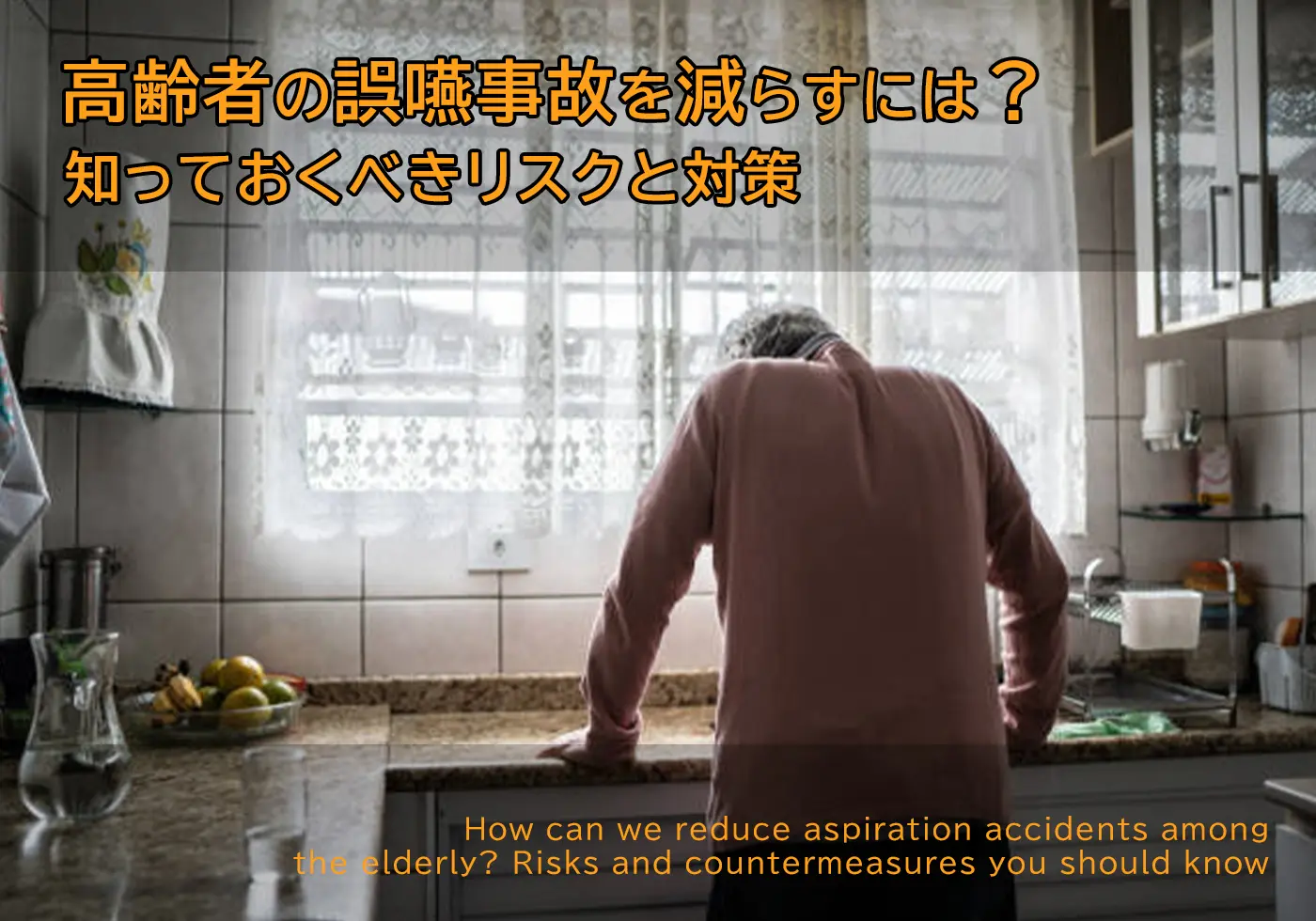





西山 耕一郎 (著)
誰でも簡単に実践できる内容です。
また、軽症者向け6週間プログラムや基礎知識、食事方法などもマンガでわかりやすく紹介しています。