日本は地震や台風、豪雨による土砂崩れなどの自然災害が頻発する国です。そのため、日々の災害対策は欠かせないと言えます。
特に高齢者は、若者のように機敏に動くことができないため、災害発生時の行動が難しく逃げ遅れるリスクが高まります。
災害時に高齢者が、できるだけ安全に避難するためにも事前に準備をする必要があります。
ここでは、高齢者が災害時に直面する問題と、災害への適切な備えや避難のポイントについて解説しています。

高齢者の多くは、判断能力や反射神経、俊敏性など身体的な衰えがどうしても現れてきます。災害が発生したときに必要な情報がすぐに得られず、避難行動の際に遅れてしまう可能性があります。
災害時に高齢者が直面する問題には、以下のようなことが挙げられます。
・情報入手が困難なことがある
高齢者の一人暮らしの場合は、災害時に必要な情報を得る手段が限られる可能性があります。例えば、停電でテレビやインターネットが使えなくなった場合に次の行動がわからなくなったり、視覚や聴覚の衰えから、ラジオや新聞の情報収集が難しかったりすることがあります。
・危機意識の低下
災害を経験していない高齢者は、自宅が最も安全だと考えてしまい、行動することをやめてしまうことがあります。目の前で起きている災害を実感しなくなった場合は、勝手に大丈夫だと誤った安心感を持ってしまうと言われております。これにより、必要な時に適切な行動が取れず、避難が遅れる可能性があります。
・自力での避難の困難さ
介護が必要な高齢者や身体的な制約を持つ高齢者は、自力での避難が難しくなります。避難所までの移動が困難であることや、災害発生時の混乱で適切な支援を受けられないことなどが挙げられます。また避難途中での事故(転倒など)も他の高齢者に比べてリスクが高まります。
・避難生活への適応困難
避難所や仮住まいでは、普段の生活環境とは異なりストレスが発生します。特にプライバシーの欠如、慣れない生活環境、不慣れな食事、睡眠不足などは高齢者にとって大きな負担です。これらは心理的なストレスの増加、既存の健康問題の悪化、認知症状の進行などを引き起こすと言われております。
■ 避難場所の確認

高齢者に限らず、避難場所を事前に知っておくことは、災害発生時に混乱することなく迅速に安全な場所へ移動することができます。
災害で避難場所が使えない場合も考え、最寄りの避難場所は複数確認しておくようにしましょう。
■ 避難経路の確認

避難場所の次は、最も安全でアクセスしやすいルートを選ぶことになります。これは移動に困難を伴う高齢者にとって特に重要です。
またルートはひとつだけでなく、あらゆる想定を考え、自宅から避難場所まで複数のルートを確認し、可能であれば事前に歩いてみることが望ましいです。これにより実際の避難時の不安を減らすことができます。
■ 避難訓練の参加

地域が主催する避難訓練に参加することで、実際の災害時の流れを学ぶことができます。
避難訓練に参加することは、高齢者が災害時に迅速かつ安全に行動するための重要なステップです。また、自信を持って避難できるようになることは、精神的な安定にも繋がります。
■ コミュニティとの連携

コミュニティとの連携により、高齢者は災害時や緊急時に頼れる支援ネットワークを構築できます。これは避難支援・医療援助・日常生活の支援など、様々な形で役立ちます。
地域コミュニティへ参加することで災害準備や避難計画に関する情報が効果的に共有されるだけでなく、高齢者に安心感を提供することにもつながります。
■ 避難のタイミング

各自治体から発令される避難情報には、危険度の低い順から、高齢者等避難・避難指示・緊急安全確保があります。
避難のタイミングは、崖の近くや海沿いといった住居環境で異なりますが、自らの判断でその時点で最善の安全確保行動をとることが重要です。
一般的な避難タイミングは下記の通りです。
【避難警戒レベル】
| 警戒レベル5 | 命の危険!直ちに避難。 |
|---|---|
| 警戒レベル4 | 危険な場所から全員避難。 |
| 警戒レベル3 | 危険な場所から高齢者等は避難。 |
■ 避難するときに気をつけること
災害は「いつ」「どこで」起こるのか想定できません。避難がスムーズに行くように防災対策をしておくことが重要です。高齢者の避難の障害となるものは下記の通りです。
家から出る以前に、家の中での怪我は高リスクで発生します。不要な物はあらかじめ捨てておくようにしましょう。物が多ければ多いほど、災害時に落下や火災、通路を塞ぐなどの危険が増えます。
特に大きな家具は固定しておく必要があります。倒れた家具が避難の妨げになることがよくあります。転倒防止のために、大きな家具はL字金具や突っ張り棒などで固定しておくようにしましょう。
重い物や割れやすい物を棚の上やタンスの上などに置いてある場合は、なるべく地面に近い場所に置くようにしましょう。地震の際は、重い物が頭部に当たる危険があるほか、割れ物が床に落下してくると避難に支障が出ます。
災害時の避難経路確保は非常に大切です。玄関先はもちろんのこと、屋外に出られる場所の周辺や通路には物を置かないようにしましょう。収納スペースがあれば常に整理整頓して余計なものが外に出ていないようにしましょう。

災害は突然起こるため、いざという時に備えて非常用持ち出し袋を準備しておくことが大切です。
災害発生時にライフラインが停止した場合は、日常生活ができなくなります。首都直下地震などの大規模な災害発生時には、自宅の倒壊や焼失の可能性があるため、在宅避難ができないことを想定して、日頃から非常時の生活に必要な物を準備しておきましょう。
一般的なものとして災害時に備えておくべきものは下記の通りです。
【避難警戒レベル】
| 水と非常食 | 飲料水:最低でも人1人あたり1日3リットルを3日分。 |
|---|---|
| 保存食:缶詰や乾パン、レトルト食品など、開封や調理が容易で長期保存可能なもの。 | |
| 必要な医薬品と健康管理用品 | 処方薬:数日分を確保。 |
| 一般的な救急用品:絆創膏、消毒薬、包帯など。 | |
| 健康管理:血圧計や糖尿病の検査用具、予備の眼鏡や補聴器の電池。 | |
| 個人情報と重要書類 | 身分を証明する書類:運転免許証、パスポートなど。 |
| 健康保険証、緊急連絡先、医療情報カード。 | |
| 金融情報:銀行の口座情報、現金。 | |
| 衣類と保護具 | 季節に合った予備の衣類。 |
| 防寒具:毛布や寝袋。 | |
| 雨具:カッパやポンチョ。 | |
| 室内履きや屋外用の頑丈な靴。 | |
| 照明と電源 | 懐中電灯やランタン:予備の電池と共に。 |
| 手回し充電式ラジオ。 | |
| 携帯電話と充電器:ソーラー充電器や予備のバッテリー。 | |
| 衛生用品 | トイレットペーパー、ウェットティッシュ、生理用品。 |
| 手指消毒剤、ゴミ袋。 | |
| 携帯トイレ。 | |
| 生活用品 | コップ、皿、カトラリー(使い捨てタイプも便利)。 |
| 手動式缶切り、包丁。 | |
| 簡易調理器具(ポータブルガスコンロなど)。 | |
| コミュニケーションツール | 防水機能のある筆記用具とメモ帳。 |
| 地域の避難所の地図。 | |
| 快適さを提供するアイテム | 趣味の物品(本、カードゲームなど)。 |
| 折りたたみ椅子やクッション。 |
重要なことは、個々の高齢者の健康状態やニーズに応じて必要なものを準備することです。
また、これらの備品は使い慣れたものであることが望ましく、定期的に確認し、消費期限が近いものや使用期限のあるものは新しいものと交換することが必要です。
【限定エコバック付き】 山善 防災バッグ 30点 セット

災害から高齢者を守るためにできることは、これらがすべてではありません。防災意識は常に高めておき、できることはすべて準備しておくようにしましょう。
また各市区町村では、災害時に自力での避難が困難な方のための避難支援制度があります。居住区域の支援体制は調べておき、突然の災害でも混乱せず落ち着いて行動できるようにしましょう。





















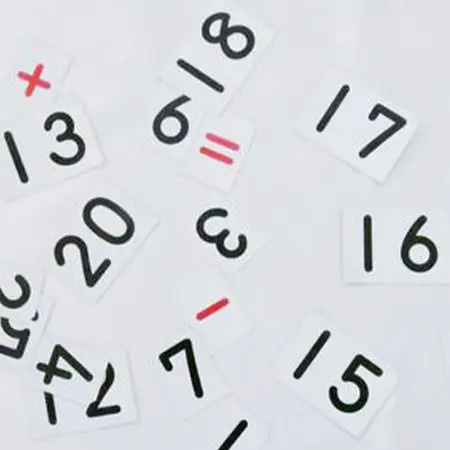

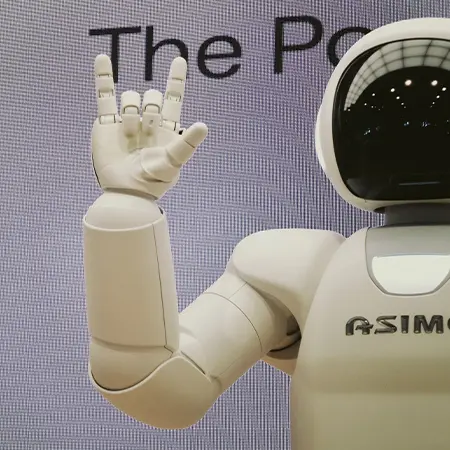





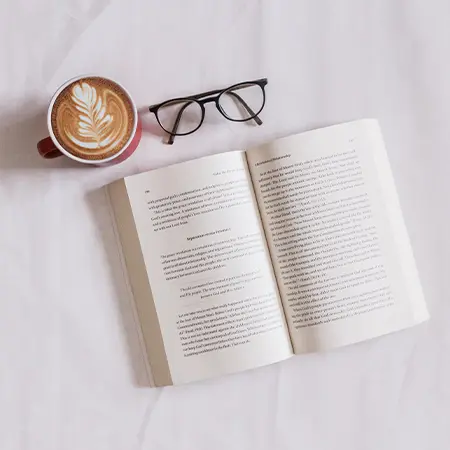































防災士監修
危険な場所から逃れるための準備。重たくて大きい物ではなく、なるべく軽量で最小限の必要物資がこのバッグに詰め込まれております。